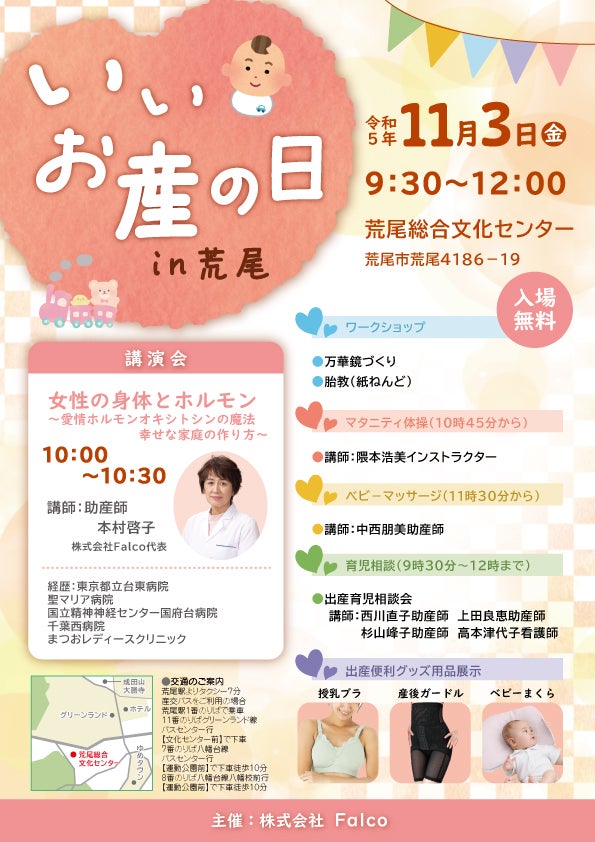ブログ記事
妊娠とお酒
妊娠中のスキンシップの重要性
簡単胎教の5選
ずぼら育児の勧め
妊娠と喫煙
妊娠貧血
11月3日「いいお産の日in荒尾」が近づきました^^
妊娠中の腹痛
妊娠高血圧症と妊娠高血圧腎症
妊娠とペット
妊娠中の夫の役割と心構え
出産する病院について